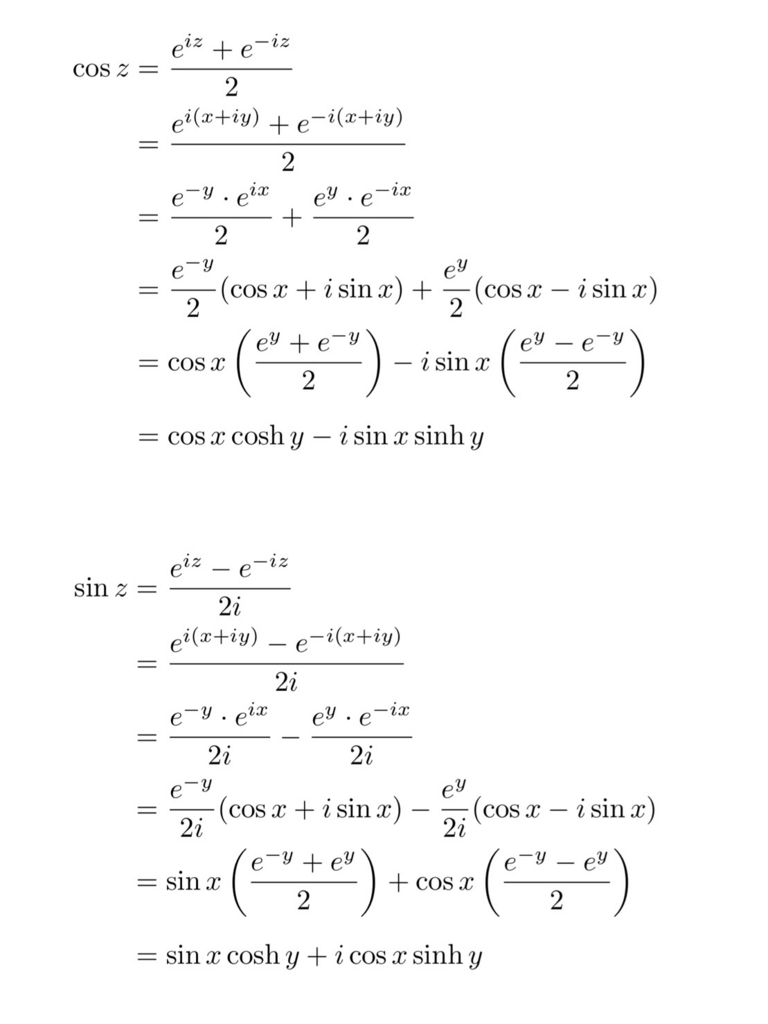目次
積分経路の変形
線積分を求めるとき, が領域
の全ての点で正則ならば, 積分経路を変形する必要はありません. なぜなら, コーシーの積分定理より
が容易にわかるからです. 積分経路の変形が必要になるのは,
の内部に
が正則でない点や領域が含まれてしまう場合です. 特に,
内部に正則でない点があるとき, その点を特異点と言います. そういう場合は, コーシーの積分定理や積分経路の変形則をうまく使って簡単な線積分に落とし込むことが必要です.
閉曲線でない場合
前回の最後で変形則を1つ示しました.
\begin{align}
\int^{}_{C_{1}}f(z)dz =\int^{}_{C_{2}}f(z)dz \nonumber
\end{align}
これはが単連結で, かつ
が全体で正則な場合の話です. 線積分の結果は始点と終点の情報だけで決まる, ということを言っています.
領域の内部に特異点があることがわかっている場合, 次のような性質で線積分の結果が同じかどうかを判定できます.
\begin{align}
\int^{}_{C_{1}}f(z)dz = \int^{}_{C_{2}}f(z)dz \nonumber
\end{align}
となる.

証明にはコーシーの積分定理を使います.
証明
とすると,
の内部全体で正則ならばコーシーの積分定理より,
\begin{align}
\int^{}_{C}f(z)dz = 0 \nonumber
\end{align}
となる. 線積分の性質から
\begin{align}
\int^{}_{C}f(z)dz &= \int^{}_{C_{1}}f(z)dz -\int^{}_{C_{2}}f(z)dz \nonumber \\
&= 0 \nonumber
\end{align}
よって
\begin{align}
\int^{}_{C_{1}}f(z)dz=\int^{}_{C_{2}}f(z)dz \nonumber
\end{align}
となる.
証明終
では例題を解いてみましょう.

(2)
(3)
例題解答4
まず関数
(1)
パラメータ
複素線積分の計算方法は
\begin{align}
\int^{}_{C}f(\varphi(t))\varphi'(t)dt \nonumber
\end{align}
なので, これに当てはめると,
\begin{align}
\int^{1}_{-1}\frac{1}{1+it}\cdot i dt &= \int^{1}_{-1}\frac{i + t}{1 + t^{2}}dt \nonumber \\
&= \int^{1}_{-1}\left(\frac{i}{1+t^{2}} +\frac{t}{1+t^{2}}\right) dt \nonumber
\end{align}
ここで, 関数
\begin{align}
\int^{1}_{-1}\left(\frac{i}{1+t^{2}} \right) dt =i\int^{1}_{-1}\left(\frac{1}{1+t^{2}} \right)dt \nonumber
\end{align}
を求めればよいのです. パラメータ
\begin{align}
t = \tan \theta \quad(\theta:-\frac{\pi}{4}\to\frac{\pi}{4}) \nonumber
\end{align}
と変数変換します. 置換積分を行います.
\begin{align}
i\int^{1}_{-1}\left(\frac{1}{1+t^{2}} \right)dt &= i\int^{\pi/4}_{-\pi/4}\frac{1}{1+\tan^{2}\theta}\cdot \frac{1}{\cos^{2}\theta}d\theta \nonumber \\
&= i\int^{\pi/4}_{-\pi/4}d\theta \nonumber \\
&= i[\theta]^{\pi/4}_{-\pi/4} = \frac{\pi i}{2} \nonumber
\end{align}
これが答えです. 1行目から2行目へは
(2)
変形則1より
\begin{align}
\varphi(t) = \sqrt{2}e^{it}-1\quad\left(t:-\frac{\pi}{4}\to\frac{\pi}{4}\right) \nonumber
\end{align}
と表せます. オイラーの公式を用いて複素数を極形式で表し,
\begin{align}
\int^{\pi/4}_{-\pi/4}\frac{1}{1 + \sqrt{2}e^{it}-1}\cdot i\sqrt{2}e^{it} dt &= i\int^{\pi/4}_{-\pi/4}\frac{\sqrt{2}e^{it}}{\sqrt{2}e^{it}}dt \nonumber \\
&= i\int^{\pi/4}_{-\pi/4}dt = \frac{\pi i}{2} \nonumber
\end{align}
ほら, (1)と同じでしょう?
(3)
閉曲線
\begin{align}
i\int^{\pi/4}_{7\pi/4}\frac{\sqrt{2}e^{it}}{\sqrt{2}e^{it}}dt &= i[\theta]^{\pi/4}_{7\pi/4} \nonumber \\
&= -\frac{3\pi i}{2} \nonumber
\end{align}
となります.
閉曲線の場合
曲線が閉曲線である場合を考えましょう.
当然, 閉曲線の内部には特異点が含まれているとします. 具体的に次のような曲線
を想定しましょう.

関数は閉曲線
の内部で, 点
を除いて正則な関数であるとします. 特異点が無ければコーシーの積分定理で線積分は
になるのですが, 特異点があるのでそうはいきません. こういう場合は, 点
を中心とする小さい円を考えます. 今は半径をそれぞれ
としましょう. そしてその円周に向かって
から切り込みを入れます. 図で示すと次のような状態です.

点を中心とする円を正の向きに1周する経路をそれぞれ
とします. また
と
をつなぐ切れ込みの経路をそれぞれ
とします. このとき, 次の図で示された領域において,
は内部全体で正則で, かつこの領域は単連結です.

閉曲線を
の3つに分割すると,
,
,
を順番につないだ結合経路に沿った
の線積分はコーシーの積分定理より
になります. つまり,
\begin{align}
\int^{}_{C'T_{1}C_{1}^{-1}T_{1}^{-1}C''T_{2}C_{2}^{-1}T_{2}^{-1}C'''}f(z)dz = 0 \nonumber
\end{align}
となります. 結合経路の線積分は, それぞれの経路に沿った線積分の和になります. また, ある経路に対し, その逆向きの経路には
\begin{align}
\int^{}_{C^{-1}}f(z)dz = -\int^{}_{C}f(z)dz \nonumber
\end{align}
という関係性があるため, 先ほどの式は,
\begin{align}
&\int^{}_{C'}+\int^{}_{T_{1}}+\int^{}_{C_{1}^{-1}}+\int^{}_{T_{1}^{-1}}+\int^{}_{C''}+\int^{}_{T_{2}}+\int^{}_{C_{2}^{-1}}+\int^{}_{T_{2}^{-1}}+\int^{}_{C'''}\nonumber \\
&=\int^{}_{C'}+\int^{}_{C_{1}^{-1}}+\int^{}_{C''}+\int^{}_{C_{2}^{-1}}+\int^{}_{C'''}\quad(f(z)dz\mbox{は省略}) \nonumber
\end{align}
となります. ですから, 上式より,
\begin{align}
\int^{}_{C} + \int^{}_{C_{1}^{-1}}+\int^{}_{C_{2}^{-1}} = 0 \nonumber \\
\therefore \quad\int^{}_{C} = \int^{}_{C_{1}} + \int^{}_{C_{2}} \nonumber
\end{align}
となります. さて, 不思議な結果が得られてしまいました. これは, 「閉曲線の内部に特異点があるなら,
に沿った線積分の結果は, 特異点を中心とする円周のに沿った線積分の和に等しい」ということです. これは閉曲線
の内部に特異点がいくつもあった場合も同様です. つまり次のように一般化できます.
関数
\begin{align}
\oint^{}_{C}f(z)dz = \sum^{m}_{k = 1}\int^{}_{C_{k}}f(z)dz \nonumber
\end{align}
となる. ただし

積分の基本公式
「変形則2を使って積分を求めたいけど, 特異点を中心とする小円の方程式が分からなきゃ積分できないのではないか」と思われるかもしれません. しかし円の半径などが分からなくても線積分を求めることができます. そのような基本公式を示します.
\begin{align}
\int^{}_{C}(z-\alpha)^{m}dz =
\begin{cases}
0 &(m \neq -1)\\
2\pi i & (m = -1)
\end{cases}
\nonumber
\end{align}
この式で注目すべきなのは, 積分の結果がや
に依存しない定数だということです. すなわち半径や特異点の座標が分からなくても線積分が求められるのです. 証明も示しておきましょう. 難しくはありません.
証明上の点はパラメータ
を用いて, オイラーの公式より,
\begin{align}
z(t) = \alpha + re^{it}\quad(t:0\to 2\pi) \nonumber
\end{align}
と表せます. 線積分の計算を行うと,
\begin{align}
\int^{}_{C}(z-\alpha)^{m}dz &= \int^{2\pi}_{0}(re^{it})^{m}(ire^{it})dt \nonumber \\
&= ir^{m+1}\int^{2\pi}_{0}e^{i(m+1)t}dt \nonumber
\end{align}のとき,
\begin{align}
ir^{m+1}\left[\frac{1}{(m+1)t}e^{i(m+1)t}\right]^{2\pi}_{0}
= 0\nonumber
\end{align}のとき,
\begin{align}
i\int^{2\pi}_{0}1dt = 2\pi i \nonumber
\end{align}
証明終
基本公式1を用いれば, 次の基本公式2が分かります.
任意の単純閉曲線
\begin{align}
\int^{}_{C}\frac{1}{z-\alpha}dz =
\begin{cases}
2\pi i & (\alpha \in C\mbox{の内部}) \\
0 & (\alpha \in C\mbox{の外部})
\end{cases}
\nonumber
\end{align}
これも証明は単純です.
証明
関数は点
以外の全ての複素平面上の点で正則です. なので
が単純閉曲線
の外部の場合,
およびその内部全体を含む領域
を考えれば, コーシーの積分定理より
\begin{align}
\int^{}_{C} = 0 \nonumber
\end{align}が
の内部の場合には, 基本公式1より
\begin{align}
\int^{}_{C} = 2\pi i
\end{align}
証明終
では例題を解いてみましょう.
関数

例題解答5
\begin{align}
\oint^{}_{C}f(z)dz = \oint^{}_{C_{1}}f(z)dz + \oint^{}_{C_{2}}f(z)dz \nonumber
\end{align}
となります.

\begin{align}
\frac{2z-2}{z(z-2)} = \frac{1}{z}+\frac{1}{z-2} \nonumber
\end{align}
と表せます.
\begin{align}
\oint^{}_{C_{1}}f(z)dz &= \oint^{}_{C_{1}}\frac{1}{z}dz+\oint^{}_{C_{1}}\frac{1}{z-2}dz \nonumber \\
&= 2\pi i + 0 = 2\pi i \nonumber
\end{align}
\begin{align}
\oint^{}_{C_{2}}f(z)dz &= \oint^{}_{C_{2}}\frac{1}{z}dz+\oint^{}_{C_{2}}\frac{1}{z-2}dz \nonumber \\
&= 0 + 2\pi i = 2\pi i \nonumber
\end{align}
となります. よって答えは,
\begin{align}
\oint^{}_{C}f(z)dz = 4\pi i \nonumber
\end{align}
私はCR関係式からだいたいこの複素積分を求め方のあたりまでが複素関数論で一番苦しいところの1つだと思っています(もう1つはリーマン面, それから解析接続のあたりでしょうか). とりあえずはおつかれさまです. 頭をなでてあげます. なでなで.
次回はコーシーの積分定理から導かれる美しい定理の1つ「コーシーの積分公式」とその一般形である「グルサの定理」を説明します.